|
|
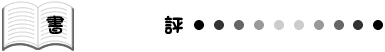 |
| 日付: |
2006/04/15
|
| タイトル: |
虹の塔 花田智子詩集
|
| 著者: |
花田智子
|
| 出版社: |
東京文芸館
|
|
書評: |
無残な夢の欠片のように、徒に泥を被るだけの人生がある。絵空事を踏み外し、大切なことは痛みを通してしか思い出せない社会もある。いざこざが耐えない人々もいる。それらとは一線を隔した花田さんの生涯が感動を呼び覚まさない筈はない。不治の病にも拘らず、忍耐と勇気の鉱脈から<希望の原石>を掘り起こし、ひたすら磨き続けていたのだ。自己瞞着に胡坐をかく教条主義者らはこれを知って恥じ入るがいい。しかも、信条告白など一言もない、この匿名性とリゴリズム。もし、クリスチャンでないとしたら、「花田さんが神」と言わざるを得まい。
逆境だからこそ燃え上がる創作意欲、これは芸術家の本分でもある。病状が悪化するに攣れ、表現手段も変わらざるを得ない。絵筆をペンに持ち替えて詩を書き、最晩年はそれこそ口述かパントマイムで、表現の場を死守することになる。ご主人にしかわからぬ表情の機微もあったことだろう。没後一周年、未発表詩を含む30余篇の作品が、彼女の霊前で、祈りの形に整えられた。本書は、病魔との闘いに打ち克った壮絶な魂の記録である。
夜中台所で
滅びる物の腐蝕が始まり
新しい生がゆるやかに立ち上がる
過去と未来がそっと手を触れる瞬間である
天使がとまどいながら時の扉をたたき
昨日と変らぬ今日が続く
初期の作品「夜の界」と比べ、何という隔たりであろう。この「日常」と題された詩には、異界の干渉に抗いながら、選ばれた天使として、この世に留まろうとする花田さんの姿がある。いつ立ち会わされるかも知れない天と地の交換劇に、内面の緊張を漲らせている。かつては、生活の匂いに包まれた彼女自身が動物や花々の中心命題であった。しかも、好んで描かれた夜の世界には、ネガをポジに変える奥深い眼差しが潜んでいたのだ。
くちなしの花の香りが
悩ましく足もとにまつわりつく
戯れる野良犬
うす燈の下に動く人影
こじんまりと出来上っている家庭
幸せを堅く閉ざす窓
自信に満ちた笑顔で挨拶して行く人
路上まで明るい花屋
賑やかな花々のおしゃべり
光の小箱を連ねた電車が
高架線の上を流れて行く
もしかしたら彼女は、持ち前の卓越した予見性によって、自らの運命の円環を閉じ、生と死の具足する世界を、既に読み終わっていたのかも知れない。夜の聖徒の賑わいが、スヒーダムの貞女に芳香を放っていた時のように。
そんな花田さんにも、ほんの束の間、輝いた昼があった。「夏の彼方に」と言う作品には母と娘が肩を並べて語り合う印象深い光景がある。明るい世界は追憶の場面にしかなく、ここで母を外在化させ、夜闇に包まれた現実の世界では天使を内在化する、詩的なレトリックは偶然の所産とは思えない。常に、そのようなものとして宇宙があり、花田さんの夜と昼があったのだろう。
淡い肌色の小千谷縮みの和服を
きりっと着込み
白っぽいパラソルの中に
真昼の光を浴びて ゆらゆらと揺らめいて
ゆるやかな微笑を浮かべ
古い駅舎の前に佇む母
・・・・
芙蓉の花が咲く頃には
母の日傘はくるりと後向きになりました
謝りたい事があるのです |
|

